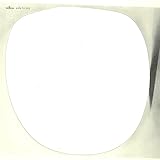オード・トゥ・ジョイ/ウィルコ
先日、CRT20周年をお祝いするイベントで、CRT発足のきっかけともなったCDコンピレーション・シリーズ“カントリー・ロックの逆襲’99”の話になって。1990年代後半のオルタナティヴ・カントリー・シーンを象徴する存在のひとつだったウィルコの、当時のライヴ映像を久々に見た。傑作2枚組『ビーイング・ゼア』の収録曲「ファー・ファー・アウェイ」。
もうメンバーもほとんど替わってしまったし、音楽性もずいぶんと様変わりしてしまっているのだけれど。バンドの中心メンバー、ジェフ・トウィーディの若き日の姿を眺めながら、あのころ受けた衝撃というか、抱いた期待感というか、そういうものを思い出して、ちょっと泣けた。感慨深かった。
オルタナ・カントリー時代の彼らが懐かしかったとか、そういうわけではなく、いかにもバンド然としたステージ上での見え方が、ね。ぐっときたのだ。胸が高鳴った。
というのも、このところのウィルコのアルバムというと、ずいぶん実験的というか、アート・ロック的というか、ノイジーというか、そういうアプローチが目立っていて。バンドとしての見え方が、初期に比べるとずいぶん変質してしまった。トウィーディの、あるいはウィルコというバンド自体の、ひねくれてはいるものの、けっしてシニカルに響きすぎない歌心の“要”の部分は変わらないとはいえ、それをごくフツーのバンド・サウンドに乗せて表出していた時期にファンになったぼくとしてはちょっと微妙な気分だったりも…。
トウィーディがソロ名義でリリースした去年の『ウォーム』と今年の『ウォーマー』で聞くことができた、わりとまっすぐな歌へのアプローチがとってもよくて。それもまた昨今のウィルコの方向性へのちょっとした疑念というか、寂しさというか、そういったものに軽い拍車をかけたり…。
でも、こうやって新作を聞いてみると、やっぱウィルコだな、と。どんなに変質したとはいえ、トウィーディはバンドで音を構築するのが好きなんだな、と。改めて思うのだ。それらソロ作での試行錯誤がバンドにもいいフィードバックをもたらしたか、今回の新作ではまたバンドならではの歌心がそれなりにわかりやすい形で戻ってきている気もするし。2002年の『ヤンキー・ホテル・フォックストロット』あたりを思い出させる曲もある。2004年の『ア・ゴースト・イズ・ボーン』ふうの音像が帰ってきた感じの曲もある。でも、それより以前、1996年の『ビーイング・ゼア』的なメロディ感覚が感じられる曲もあったりして。CRT心がうずく。
もちろん、最近のインタビューでもトウィーディは“もうありきたりなロックの在り方には飽きた”みたいな発言をしていて。確かに今回も相変わらず、そういう気分をしっかり反映した音像というか、フツーのバンド・サウンドとはまるで違う発想のアレンジ/ミックスが基本的にどの曲でもなされてはいるのだけれど。
ただ、これもこれでトウィーディなりのバンド・サウンドへの強いこだわりなのかなということがわりと受け止めやすいツクリというか。ぼくのようなデビュー当時の彼らの在り方にいまだ未練を抱いているタイプのファンも、『ヤンキー・ホテル・フォックストロット』で一気に音響派方面へとシフトチェンジした時期以降のファンも、それぞれそれなりに納得できる仕上がりだと思う。なんか、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドみたいだったりする瞬間もあり。
理屈っぽさと無垢さとを両立させながらイマジネイティヴに心象を描き出すトウィーディ独特の歌詞の世界も健在。政治的にも、文化的にも、世界がとんでもない混沌のただ中にある今、そんな時代ならではのウィルコ流の“Joy”つまり“歓喜”を様々な形で模索した1枚だ。